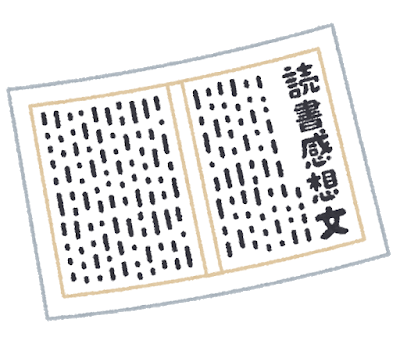読んだ本
・新装版 ムーミン谷の彗星(講談社文庫)
https://www.moomin.co.jp/books/2407
内容と感想
実は44才で初めてのムーミンです。もちろんムーミンというキャラクタは知っていましたが、ストーリーは全く知りませんでした。アニメも観たことがなかったのです。で、なんで急にどうしたの?と思うわけですよね。
今、小5になる娘がいまして、その子がムーミンを読んでハマっておりまして、話題についていけるようにと読みました。
ムーミン谷の彗星は、童話チックな内容を想像していたらちょっと違っていて、少し怖い感じもあるストーリーでした。ムーミン谷に彗星が迫ってきて、それを調べるために天文台に向かって…
スニフやスナフキンもすべてが初登場ということで、とても新鮮な感じです。スノークのおじょうさんとムーミンの出会いも素敵でした。
年甲斐もなくムーミン谷は最後、どうなってしまうのだろうとハラハラしました。とはいえ、決してハラハラドキドキの連続で手に汗を握る、というものではなく、ムーミンの不思議な世界と愉快なキャラクタが、なんだかふんわりした気持ちにさせてくれる本です。
1日半くらいで読み終わったら、娘が「楽しいムーミン一家」を貸してくれたので、今読んでいます。
ちなみに
少し前に飯能のムーミンバレーパークにも行ったのですが、今行ったらもっと楽しいかもという気になっています。残念ながら休園していますが…
・ムーミンバレーパーク・メッツァビレッジ
https://metsa-hanno.com/