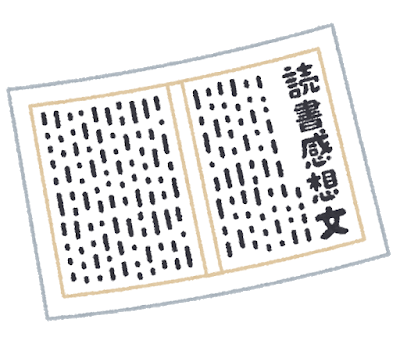読んだ本
・アセンブラで読み解くプログラムの仕組み
https://gihyo.jp/dp/ebook/2011/978-4-7741-4890-8
内容と感想
数年前に読んだことがあったのですが、そのときは「ふーん」くらいの感想で特に印象に残ってはいませんでした。
低レイヤを知りたい人のためのCコンパイラ作成入門 を読んで実際に関数を実装したところくらいでもうちょっとアセンブラを理解したいなと思って、再度読みました。
以前よりもアセンブラに慣れてきたからか、思ったよりさらっと読めたのと、内容も理解できた気がします。
アドレッシングや関数の呼び出しや引数の取り扱いは低レイヤを知りたい人のためのCコンパイラ作成入門 でやっている内容とほぼ同じ(ただし、低レイヤ〜がAMD64で、アセンブラで〜がx86なので、引数の渡し方が違ったりはしています。)だったので、本当にスッと理解できた気がします。
気だけかもしれません。
共有ライブラリのところが、低レイヤ本の方ではやっていないテーマのようで、共有するための工夫というか苦労というかあるのだな、と分かって面白かったです。
最後の「継続は続く」はもともと、継続をよく理解できていないので、やっぱりあまり理解できませんでした。
今度はSchemeの勉強かな。
ちなみに
次は、[試して理解] Linuxのしくみ を読む予定です。
家にいる時間が増えてきたので、しっかりと力をつけたいと思います!