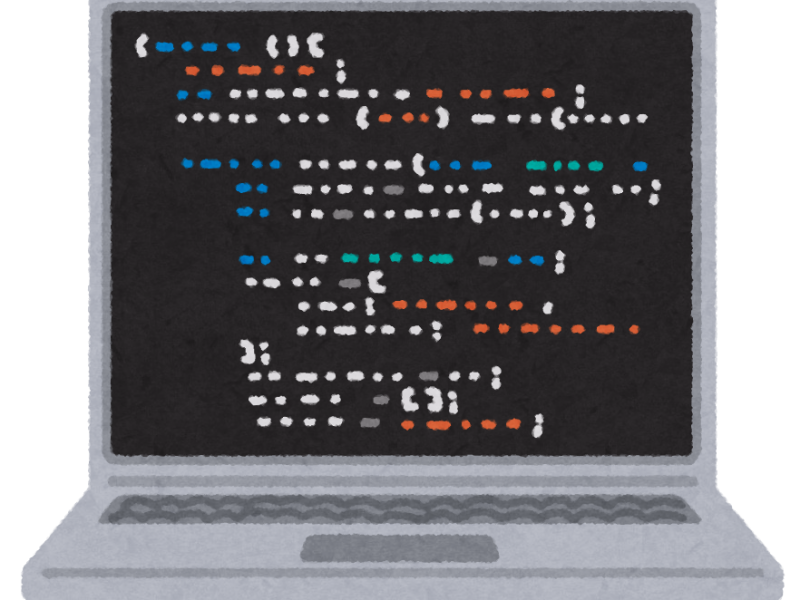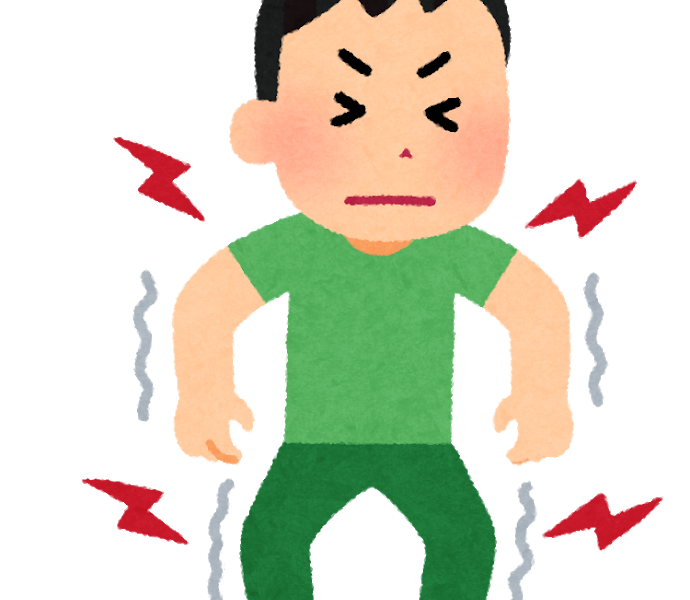はじめに
子どもたちが夏休みに突入しました。パパにとっても忙しい季節ですね。今年はすでに日帰りを含めてキャンプの予定が3つ入っています。最初のキャンプの記録です。
最初のキャンプは家族だけの二泊三日のキャンプでした。
1日目
目的地は、山梨県北杜市です。すんなり行けば2時間半程度の距離ですが、中央道が混むかもと思って、余裕を持って朝9時前に出発。この時点でGoogleマップでは多少の渋滞の情報がでていました。
あきる野ICを過ぎるあたりから、明らかに渋滞に入ってしまった感じがありました。しかし、迂回路もよくわからないので、我慢して進むと八王子JCTに近づくに連れ、どんどん動かなくなります。これはやばい。ほとんど動いているのかいないのかわからないような感じになりました。もう歩くのと変わらないんじゃ?という状況でした。高速に乗る前にトイレは済ましていたものの、3時間近く乗り続けていたため、さすがに限界が近づきつつある状況に。なんとか八王子JCTを過ぎた後、次のPAに入れる気がしなかったので、相模湖東ICでいったん高速を降りることに。
高速を降りてすぐの道(国道20号)も山梨方面はすごく混んでいたので、いちど逆方向に進み、とりあえず最初に見つけたお店に駆け込みました。
トイレの後に、おまんじゅうと野沢菜を買いました。お腹が空いていたこともあり、おまんじゅうを美味しくいただきました。その後、顔はめしていたら、道行く車のドライバーたちに微笑ましく見られて照れました。
ついでにお昼を近くのお蕎麦屋さんでいただいて、気を取り直し出発。相模湖ICから中央道に戻りました。渋滞ではあるものの、八王子付近のような状況ではなく、それなりに進み上野原ICを抜けた後くらいからは割とスムーズに進めるようになりました。良かった。結局予定よりも大幅に遅い16時ころ、宿泊予定のキャンプ場に到着しました。無事に着いて良かったです。
キャンプ場はこちらです。
山の斜面にあるキャンプ場で、とてもすばらしい見晴らしを楽しめました。以前は、ヤギもいたみたいなのですが、今はいなくなってしまったようです。残念。スタッフの方(特におじいさんとおばあさん)がとても親切で、素敵なところでしたよ。夜、炊事場の水がでなくなったのですが、おじいさんがポンプを何かしてくれたらしく、割とすぐに出るようになりました。ありがとうございました。後で伺った話では、サントリーの南アルプスの天然水と同じ井戸水を汲み上げているとのことでした。

下の写真は、キャンプ場からの眺めです。残念ながら、雲に隠れていますが、甲斐駒ヶ岳の姿を見ることができます。もう15年ほど前に旅行で行った、スイスのアイガー、メンヒ、ユングフラウを観たときと同じような印象でした。南アルプスと呼ばれる理由が少し分かった気がします。雄大さを感じました。昔の人が山に何か神聖なものを感じたのも分かる気がします。(気がするだけかもですが。。)

この日は、夜ごはんをいただいて、ゆっくり眠りました。
2日目
2日目は川遊びです!キャンプ場のおじいさんに、「精進ヶ滝」に向かう遊歩道にある「一の滝」を紹介してもらいました。道を聞いていても若干心細くなるような道を進むこと15分、駐車場に到着です。そこから、遊歩道を10分ほど歩くと「一の滝」に到着です。途中、フォッサマグナの案内などもあったのですが、子どもたちは興味ないようで、残念ながらスルーしました。

写真では小さく見えますが、滝つぼに近づくと結構な圧がありました。滝行って見た目よりツライかもと感じました。水がたいへん透き通るようにきれいで、あまり魚は見つけられませんでした。せっかく来たので、石をいくつか拾ってみたのですが、種類はあまり多くなくて、似たような石ばかりでした。事前に下調べして来るべきでしたが、仕事が忙しかったため、あまり下調べできず残念でした。小さい石を少しいただいて帰ったので、後で調べてみようと思います。
お昼を食べに町に下りて、道の駅でランチにしました。遅い時間だったにもかかわらず結構混んでいました。「おざら」という地域の麺料理をいただこうと思ったのですが、品切れらしく、甲斐駒ヶ岳天丼をいただきました。野菜がとても美味しかったです。
夕飯の食材を買ったり、温泉に入ったりして、キャンプ場に戻りました。2日目の夕飯はパエリアとミネストローネでした。焼き肉よりも落ち着いて食べることができました。
3日目
最終日は、朝起きてテントの撤去などをしました。9時過ぎにキャンプ場を後にしました。とても素敵なところだったので、ちょっと名残惜しい気持ちもありました。
うちでは「アルプスの少女ハイジ」ブームが来ていることもあり、ハイジの村に向かいました。
駐車場が結構混んでいたのですが、敷地が広いこともあり、中はゆったりとしていました。ロッテンマイヤーズカフェで、カップを持って帰ることができるヤギのミルクのアイスクリームを食べてから、ハイジの村の中を散策しました。ヤギにえさをあげたり、おんじの山小屋を観たり。遊具のコーナーで少し遊んで、お昼を食べにペーター館へ向かいました。2日目に食べそこねた「おざら」をいただくことができたので、満足でした。おざらは武蔵野うどんとよく似ていて、地理的にも遠くないのだな、と感じることができました。
帰りは高速もそれほどの渋滞はなく、割とスムーズに進み、予定どおりくらいで帰宅できました。夕飯はハイジの村で買った「白パン」でした。美味しかったです。
まとめ
山梨県は感染対策もしっかりしていて、うちもしっかり気をつけて過ごしました。安心と安全の中でのキャンプを過ごすことができ、楽しい思い出をありがとうございました。山梨県北杜市のみなさんと家族に感謝です。
ちなみに、買って帰ったソーセージが美味しかったので、ふるさと納税しました!