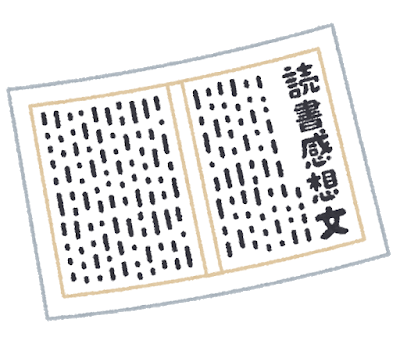読んだ本を記録しておくエントリーです。
読んだ本
内容と感想
第1章から第5章までありました。各章が割と独立しているので、どこからでも読むことができると思います。全体通してもさっと読めるので、前から読むほうが良いとも思います。
著者は、戦後の日本型循環モデルが既に崩壊しているにもかかわらず、それを無理に維持しようとしていることが、さらに問題を深くしているというふうに考えているのかな、と感じました。
私も全く同感ですが、一方で、世の中をリードする層(政治家だったり大企業の重役だったり)は従来の日本型循環モデルの中で成功してきた人たちなので、それらの人にドラスティックな変革を期待するのは難しいのかな〜とも思います。
この本でも、以前に読んだアンダークラスと同様に、日本が階級社会とでも言えるような状態になっていて、階級間の分離が問題であると思っているようです。
そういう状態は確かにあって、同じ階級の中で閉じてしまっていて、異なる階級が不可視になってしまっていることで、問題が見えにくくなってしまっているというふうに思います。割と短期間に同じような内容の本を読んでいることから、自分の問題意識は、このあたりにあるんだな、と再認識しました。
東大の入学式での上野先生のスピーチが話題になりました。あのスピーチと通じる内容だと思います。私は、上野先生のスピーチはとても素晴らしいものだったと思っています。
平成31年度東京大学学部入学式 祝辞
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/president/b_message31_03.html
第3章が、労働をテーマにした章で、個人的に一番気になったところでした。
労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎さんが述べていた「ジョブ型」と「メンバーシップ型」に触れて、ジョブ型への移行を目指すべきという内容でした。
私もメンバーシップ型の維持は限界にあると思っていて、ジョブ型への移行が必要だと思う一方で、終身雇用を前提としてきた中で急に移行できないというのも頷けます。やっぱり誰しも、自分の生活は大事なので。
ITエンジニアの世界では転職は割と一般的なようなので、技術がある程度はっきりと測定できるようになると、ジョブ型への移行が進むのかなぁと感じます。
社会への閉塞感を感じている人にとって、何が問題なのかを整理するためのきっかけになる本だと思いました。