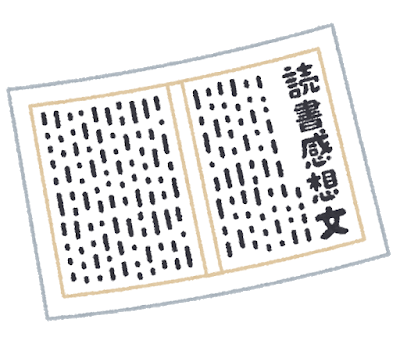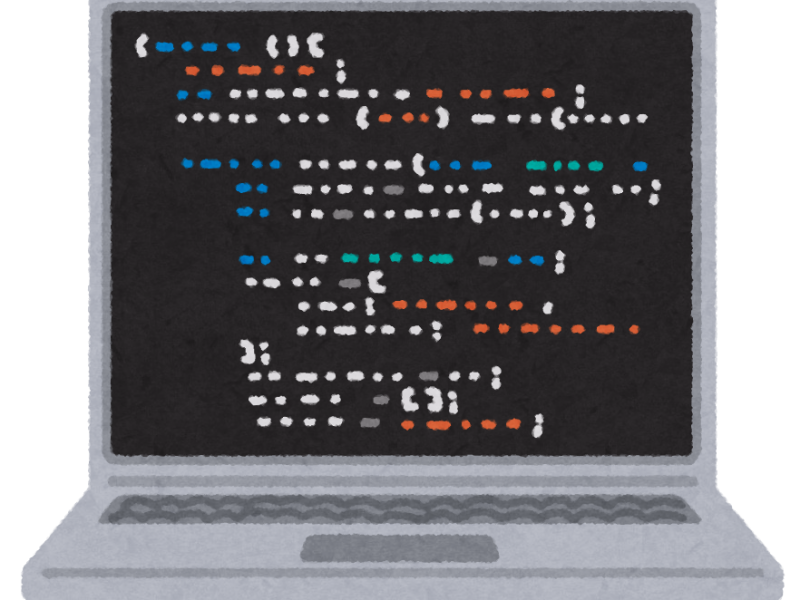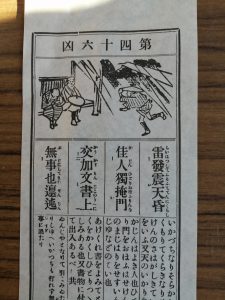はじめに
年末年始が9連休だということに11月の下旬に気づき、慌てて旅行の計画を建てようとして、近場の長野県佐久市に行くことにした、というお話です。
なぜ佐久市なのか?
昔の知り合いが住んでいるから、というのが大きな理由の一つです。あと、知り合いの一人が、千曲川の氾濫で被災したというので、そのお見舞いも兼ねました。
かれこれ20年近く前ですが、お金はないが暇はあるというときに、ヒッチハイクでなんとなく本州をほとんど一周したことがありました。そのときに、佐久平駅近くのイオンモール付近で八千穂方面に行こうとしていて、乗せていただいたのがきっかけです。その後もお付き合いが続いていて、それだけでとてもありがたいことです。
2019年10月の台風19号の影響で、千曲川が氾濫したというのがニュースになっていましたが、佐久市でも大きな影響が出たらしいというので、行ったところでお役に立つわけではないのですが、久しぶりに訪問しないと、という思いから訪問することにしました。
特に、うちの子どもたちは被災体験などがないので、そのときの写真や話を聞かせてもらうことで、災害の怖さを知るきっかけにしてもらいたいというのもありました。
みなさん元気で何よりでした
実際の堤防の決壊跡を見たり、滑津川(千曲川の支流)の氾濫場所を見たりしました。千曲川だけだと思っていたので、支流も氾濫していたということを知って驚きました。支流でも油断できませんね。
被災状況の大きさも驚きでしたが、みなさんが本当の元気そうで、それが驚きでもあり、とてもうれしくもありました。よく元気づけに訪問したら、逆に元気をもらうという話を聞きますが、本当なんですね。すごいなぁと思いました。
せっかくなので
主目的は災害の勉強でしたが、せっかくの旅行なのでということで星空観察とスケートをやる予定で考えていました。
星空観察
佐久市にはうすだスタードームという天文台のようなところがあるそうです(初めて知りました)。標高が高いからだと思うのですが、星がよく見えるということで、星を観察しようと思ったのです。うすだスタードーム(訪問した日は年末年始の休館日)の駐車場がよく見えると聞いていたのですが、雪が残っているかも(うちの車はノーマルタイヤ)ということと、夕方から曇りだったのとで断念しました。長野県の冬を甘く見てはいけない!
うすだスタードーム
https://www.city.saku.nagano.jp/star-dome/
スケート
スケート自体は所沢(東大和駅前のスケート場に行くことが多いです)でもできますが、せっかくの本場ということでスケート場に行きました。
風越公園アイスアリーナ
https://www.kazakoshi-park.jp/ice-arena/
もっと早く計画していればカーリングの体験にも申し込めたかも、という思いがありますが、家族全員たいしてスケートできないので、まずはスケートからしっかり始めようと考えました。
天気がよければアイスパークの方の屋外スケートリンクで滑ろうと思ったのですが、あいにくの雨雪まじりだったので、屋内スケートリンクで滑りました。
オリンピックマークがあったので、長野五輪のときの会場だったのかも、という気がします。素敵な会場でした。
おわりに
子どもたちも楽しめ、パパももちろん楽しんで、とても素晴らしい1泊2日でした。いろいろと案内してもらったり、忙しい中集まってくださったり、お世話になった皆さんに本当に感謝でいっぱいです!